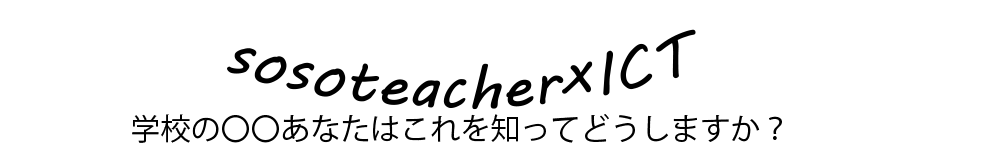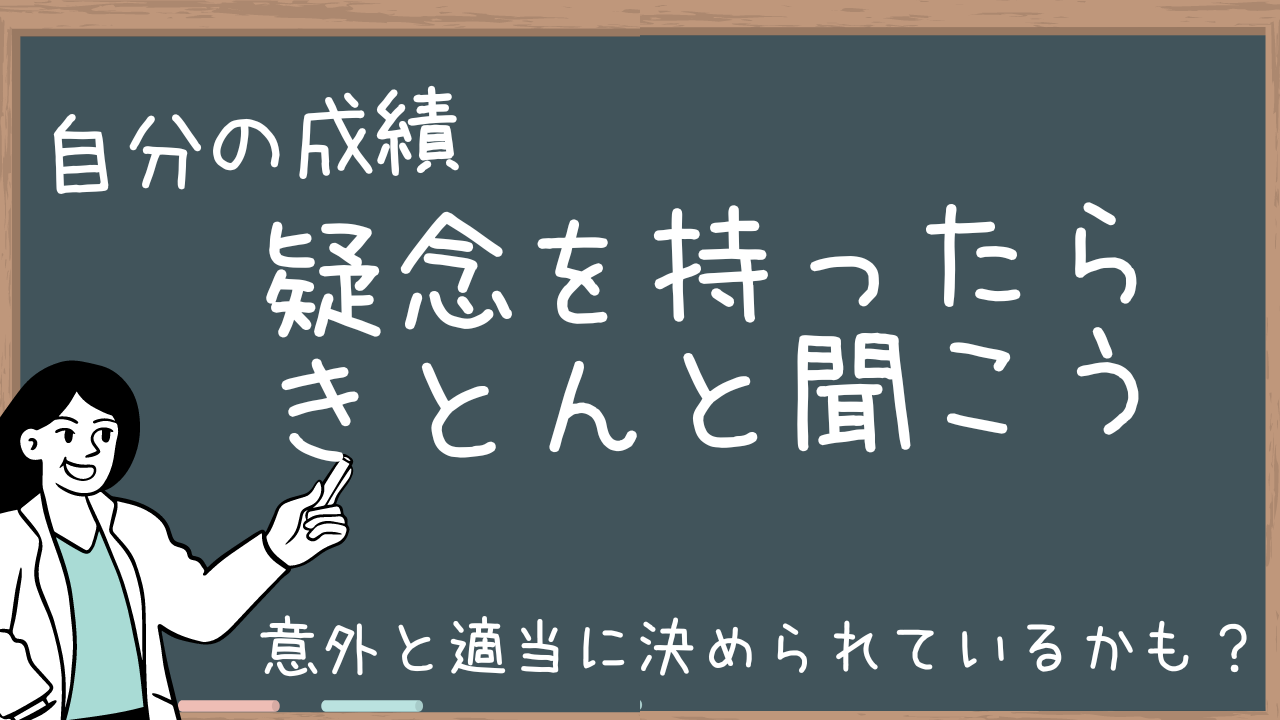そろそろ1学期も終わり3年生にとっては、指定校推薦に必要な成績が出揃う時期ですね。ここで学生のみなさんに一つ聞きます。
自分の成績にきちんと納得していますか?
提出物も出して、テストでも点数を取っているのに。体育ではきちんと結果を出しているのに。など自分ではきちんと取り組んでいい成績が出るはずだったのに・・・
なんてことありますよね。
今日はそんな成績にまつわる話をしていきますので生徒の中で成績に不満のある方や保護者の方で成績ってどう決めているのかと疑問に思っている方は是非読んでいって下さい。
そして、学校関係者の方へ先に謝っておきます。こんな記事書いてごめんなさいね。ですが、この記事が書かれる原因は現場で働いている方があまりにも雑かつ適当に成績を決めすぎているので書くんです。
成績の不満は必ず解き明かすべし
成績が分かったらまずすること
通知表=成績です。この用紙が手元に届いたらまずすることは、自分と同等レベルの友達の評価値を種集することです。なかなか言いにくい事かもしれませんが是非聞いてみましょう。そして、自分よりも点数が低いのに、欠席が多いのに、提出物を出していないのに、なーぜーか成績が上の子が居たら要注意です。そもそも自分は頑張っているのに成績が5が付かなかったり、思っていた評価と異なっていた時点で担当の教員へ必ず聞きにいきましょう。
まず、聞きにいく際に知っておくべき知識をここで伝授しておきます。
今の学生に適用されている学校での成績の決め方は観点別評価
観点別評価って何?となりますよね。簡単に言うと3観点と言われる「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」のことです。そして授業を実施している教員はこの3観点に合わせて教材を作成したり、テストを作成しなくてはなりません。ここで薄ら気付くかもしれませんが、テストだけで評価した。というのはもうダメなんです。昔はテストの点数で判断したりした時代もありましたが、今は多様性という言葉が多く使われるようになり、上記のようになったんです。
この3観点はどう評価されるのかを簡単にですが紹介します。
「知識・技能」
例:テストでの点数=どれだけ知識を身に付けたかを判断します。
「思考・判断・表現」
例:授業での発表やプレゼン、提出物での判断となります。要は、周りの人と異なり独自性を持って取り組めているかを判断することになります。もちろんですが、独自性があっても題目と違った作成ではNGです。
「主体的に学習に取り組む態度」
例:自分の成績を伸ばすためにどのように取り組んでいたか、生徒同士の相互評価などとなってきます。
詳細は文部科学省がきちんと資料を出しているのでこちらを読んでみてください。
「新学習指導要領 学習評価の改善点」P.43~になります。
どのように評価をされたかを聞く
上記での3観点をそれぞれどの評価物で評価を行ったか。そして評価基準はどのような基準であったか知ることできます。
①成績について知りたいと言う
よく居るんですが、感情的になって聞きに来る子が必ずいるのですがここで感情的になってもまず何も良いことは無いとだけ言っておきます。
なので、友達と束になって行っていいんですがまずは冷静な心で担当の先生に、「成績について聞きたいので時間良いですか?」と聞きましょう。
部活が、、、や会議が、、、と言われたら「それでは、いつの何時なら大丈夫ですか?」とアポイントを取りましょう。
②成績の評価物が何であったかを聞く
ここは結構重要です。先生に必ず下記の事項を聞きましょう。
(1)◯学期の成績で評価された評価物を全て教えてもらう。
(2)どの評価物がどの観点での評価物か教えてもらう。
(3)その評価物がどのような基準で評価されたかを教えてもらう。
聞いた評価基準と自分の提出物が適切に評価をされているかを調べる
先生に評価物から評価基準まで教えてもらったら自分でその評価基準に達しているのかをきちんと見比べる。
当たり前ですが、先生も人間ですし1対1で授業から評価をしている訳ではないのでミスはあって当然です。なので、今一度自分の目で再度確認することは重要です。
友達とどう違ったかを見比べる
ここまでできたら友達の評価物とどう違ったかを見比べましょう。些細な点で減点や評価が違うことはあります。その点についてメモをとりもし自分のミスで評価が下がっているのであれば次の学期に備えましょう。ですが、あからさま同じなのに評価が異なっていれば必ず担当の教員へ申し出ましょう。
成績を付けている裏側の話
正直今となっては、真面目に成績を付けている先生がほとんどと言っても過言ではありませんが、残念なことに独自の解釈や方法で成績を付けている先生がいるのが現状です。
それでは、成績ってどのように付けられているのかを話していきます。
コツコツとチリも積もれば山となる
本当にこの通りで、コツコツと少しずつ提出物や発表などをさせて少ない授業時間の中評価できる物を生徒に出させています。ですが、ここで残念なのが個人的な感情を入れて評価している教員がいることです。
私が現役の頃はルーブリックという方法で評価をしており、評価が終われば生徒にそのルーブリックを公表して再提出を可としていました。なぜなら、そもそも学習とは定着させるものであり、定着した知識や思考をさらに伸ばすのが教育と考えているからです。このことについては別記事で紹介したいと思います。
ここで言いたいのは、コツコツやっている人の反面焦って評価物を回収してまとめて評価をしていることがあるのです。当たり前ですが、まとめて評価物を回収すれば莫大な量になり、人間なので飽きや疲労がくればそこからガサツになるのは誰もが考えれば分かることです。
部活動を評価に加味する
稀にですが、◯◯ちゃんは◯◯部なのに・・・と評価に加味されることがありますが、これはNGです。まず、部活動は教育課程外であり、授業とは別物です。
例:美術部なのに、吹奏楽部なのに、サッカー部なのに
教員の中には、紹介したように部活動を理由に成績を下げる教員がいますが、これは平等性に欠けることなので評価の対象としてその点を踏まえることは望ましく無いです。
残念なことに私が現役の時はこの点を成績に加味してトラブルになっていた教員を知っています。残念な話ですね。
成績の話をされた際に、「部活」というキーワードが出て来た時点で成績を再度検討する余地があるということになります。
通称顔点
教員の中には、こいつにはこの成績をあげたくないと個人的な感情を入れる人がいます。そんな人がやることが顔点という作業です。
簡単に言ってしまえば、成績の換算データに1行付け加えてなぞの点数を上乗せするんです。こいつ俺が思っていた以上に成績が・・・となるとこういった作業をします。特に体育科によく起きる傾向にあって、自分の部活動生徒の成績を少しでも上げたいと思っている人が少なからず居てやってしまうんですね。
後は教員も人間ですから、お気に入りの生徒などいるとこいつは頑張っているからと言って謎な加算点を付け加える傾向にあります。
これはまさに教員へ成績の開示をしないと見えない部分なんです。
そして、私が目撃したのは体育委員会に入っていないと成績で5は出ないという謎の体育科の方針です。残念ですが、これが世に出れば叩かれること間違いなしです。そもそも委員会で選ばれる生徒に人数には限られており、その授業を受講している生徒全員への平等の扱いには著しく欠けるからです。
見込み点という曖昧な点数
定期考査や小テストなど、未受験のテストがある学校や教員によってそのテストの見込み点といものを入れます。
まさに成績の狂いはこの点数と言っても過言ではないです。私が教員をしていた頃にこの見込み点についてきちんと方針を定めていた学校は耳にしたことがありません。
なので、もし見込み点というのを使っている学校がいた場合は①その見込み点はなぜ付けたのか②算出の方法は?③根拠のある見込み点なのかをきちんと聞きましょう。
ここでもし根拠に欠ける発言や方針を打ち出していることであればその点数を成績に加味することはNGです。
そして、定期考査は学校が定めた日程で受験することが当たり前ですが心身上受験が難しいまたは、出来ない場合は学校側は当該生徒を平等に扱うまたは、同等に扱う義務があります。その返答に対してNoと言ってしまえば考査関係の点数が0点というのは致し方ないということになりますので、注意しましょう。
成績に疑念は持つべき
ここまで読んでいただきお子さんを含め保護者の方は、どう思いましたか?AIが進化する時代ですが成績においては、AIには出来ない部分もあるので人間が行います。だからこそ、ミスや感情が入ることがあります。今まで教員をやってきてこんなに理不尽なことがあるのか?と声を出してきましたが、校長を含め管理職は「教科が決めたことだから」と見て見ぬふりをして来た管理職が多かったので今回はこのような記事を書きました。
是非これを機にお子さんとコミュニケーションを図り、子供が少しでも成績に疑念を抱いているのであれば学校へ聞いてみてください。
ニュースでも知っている通り本当に学校の質そのものは低迷しており、回復する兆しすら無い状況です。大学4年生で採用試験に合格して、社会人1年目からろくな研修も受けずに社会に放り出されて生徒からは先生!と慕ってくれる環境に入るんです。自分の言うことを聞いてくれる人間を相手に毎日仕事をしていれば、少しでも自分のことに疑念や質問・開示請求をされると教員の真っ先な返答は、「何だあいつ!あいつがまともにやってないからだろ!」です。
そんな教員こそ、基本は雑な成績を付けている傾向にあるからこそ、きちんと説明責任を果たさせて自分のミスに気づかせると同時に、お子さんがやったことを正当に評価してもらいましょう。