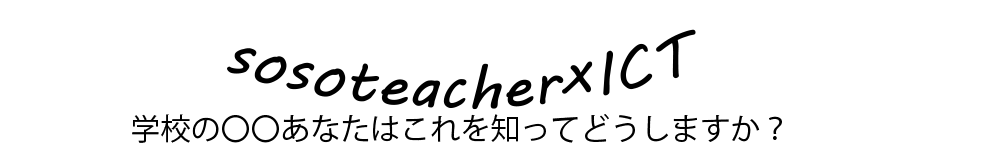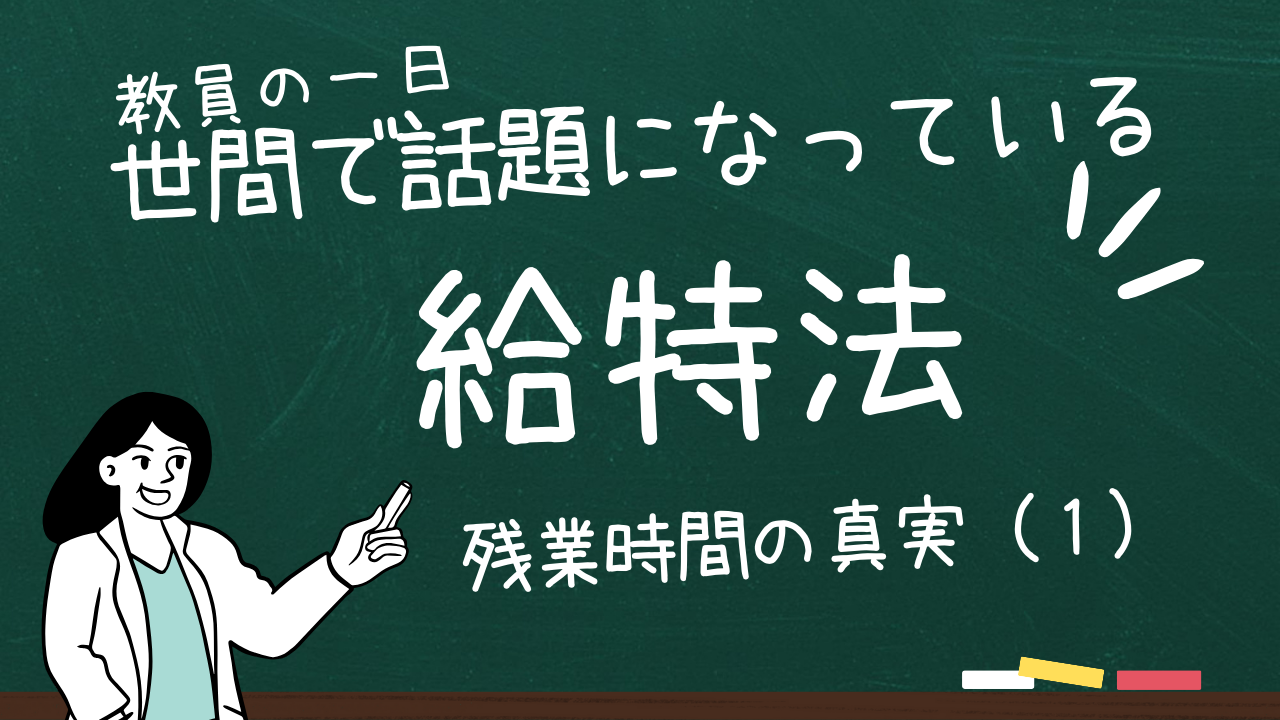最近ニュースで話題になっている給特法について触れていきたいと思います。
- なぜ、今になって給特法が引き上げになったのか
- なぜ、この引き上げに現場の教員は拒むのか
- 残業時間の真実
引き上げのタイミング
このタイミングで引き上げになった要因は、2024年に話題になった民間企業の賃金満額引き上げがひとつの要因です。
公務員の給料は、民間企業と同等に近い賃金となっています。当たり前ですが、民間企業が不景気であれば賃金は下がりますし、景気が回復すれば賃金が上がるようになっているはず、、、なんです。
ですが、実際に現場にいた教員からすると賃金が下がった感覚は感じるが、上がった感覚は正直無いんです。その例が東日本大震災です。災害を機に景気が下がったので当たり前ですが賃金も下がりました。ですがそこから賃金が元に戻ったかと言われると実際に戻っていないと感じています。要は下がったら下がりぱなし?と思うんですね。
そして、今回は賃金の中に含まれている給特法の引き上げをします!というニュースです。何も知らない人からしたら教員の給料が上がるんだーと思う方もいるかもしれませんが、実際の労働に対して本当に10%以上で適正なのか?についても触れていきましょう。
なぜ、給特法の引き上げに反対が出たのか
世間からしたら、嬉しいなずなのでは?と思うかもしれませんが実際の教員の残業時間は、1日2時間~4時間は当たり前となっています。
就業時間は、8時30分~17時00分だが実際に勤務を開始しているのは、7時00分で帰る時間は20時00分。
正直これが現実なんです。1日で4時間30分の残業が当たり前となっているんです。そして、今回の給特法はこの残業時間が多いから引き上げをしましょう。となったんです。
ですが、給特法が引き上げられたからと言ってこの残業時間の解決にはなっていないんです。逆に言えば、教員をバカにしていますか?と言われてもおかしくはない対応でもあるんです。
なので、一部の教員からは根本的な残業時間の解決には至っていないから給特法の引き上げに反対し、そもそもの働き方の見直しをしてくれと言っているんですね。
残業時間の真実
そもそもなぜ、そんなに残業をしなくてはならないのか一日の勤務を見ながら追って行きたいと思います。
朝の電話対応
教員の一日は、この電話対応からスタートします。朝保護者の方から欠席の連絡を頂くことは毎日です。そしてその電話をわざわざ担任の先生へ回している余裕はないので電話を受け取った人が担任へ事務連絡を行います。
電話が鳴っていない日の方が少ないです。そして。電話の対応が終わったらその日に使用する教材の見直しや予習を行います。
7時00分~8時30分
朝の打ち合わせから朝の会
勤務開始の8時30分から約10分程度で教職員の打ち合わせがあります。1日の流れから生徒対応の件まで細かく全体で共通認識を持ちます。その後は、各クラスへ行き小・中学校では朝の会、高校ではショートホームルーム(SHR)を行います。
8時30分~8時45分
1時間目~4時間目までの授業
1時間目は大体8時50分から開始し、4時間目の終わりが12時40分です。
空き時間というのも存在しますが、その時間で次の授業で使用するプリントの作成から小テストの作成・採点・成績入力まで行います。
8時50分~12時40分
昼休み
小・中学校の場合は担任がクラスへ行き給食指導を行います。なので、実際はお昼と言いますが生徒の机間巡視しての観察や生徒とのコミュニケーション落ち着いてお昼を食べるということはできません。
高校の教員でも、クラスの見回りや校内の巡回などがあったりするので実際はゆっくり座って食べているということはあまりないです。
12時40分~13時30分
5時間目~6時間目
ここから午後の授業です。午後は2時間分しかないですが、時間が空いていれば小学校であれば下校指導の準備、中学校・高校だと部活動の準備なんかがあります。
また、午後に会議や外部の方との打ち合わせなんかが入ることがあるのでその対応もこの2時間の間で行います。
13時30分~15時40分
清掃指導
やっと一日の授業が終わったと生徒と同じ気持ちになるのもこの時間です。
ですが、授業が終わっても一斉清掃があるので、その指導を行います。清掃指導も教員が率先して行わないと清掃をしない生徒もいれば、率先してやってくれる生徒とまちまちなので、そのニーズに合わせて指導を行います。
15時40分~16時00分
放課後・部活動
小学校であれば、下校して家庭への連絡から提出物の確認・採点・評価を行います。
その量も膨大で回収した教科×生徒人数分なので、仮に4教科集め生徒が30人なら、120枚を見なくてはならないんですね。これは、中学校も高校も同じです。
部活動については、中学校では18時頃まで、高校では顧問の裁量で行われます。
少なくともほとんどの教員が何かしらの部活動を受け持っているのでその指導を行います。
私も運動部を持っておりほとんどが19時まで活動を行っていました。
中学校や高校は部活動の指導が終わってから家庭への連絡や、提出部の評価などを行います。
16時00分~19時00分
教員の一日
ここまでが教員の一日です。正直椅子に座っている時間よりも立っている時間の方が明らかに多いです。スマートウォッチを付けて勤務していた頃は、一日に1万歩は普通に歩いていました。
そして、教員の給特法が引き上げになる理由は何となく察していただけましたでしょうか。
この残業問題に正面から取り組んでいる教育委員会は正直一部です。ですが、私からしたらこの問題を大きく変えるキーは学校長要は校長先生と思っています。校長が率先して学校の取り組みを根本から変えようとしない限り変わらないんです。
数年後の未来本当に教員は足りているのでしょうか。私の答えは、Noです。
この記事を読んでわかるように本当に教員をやりたいと若手が思いますか?思いませんよ。
この記事を読んだ学校関係の皆さん是非組織の改革を進めていきましょう。進めないと明日にも学校から教員がいなくなりますよ。
ここまで書いてなんですが、私の本音はこの残業時間問題を根本から変えられない原因は、教員にあると考えています。そしてこの後に掲載される記事を読んで頂いたらその残業問題の本当の原因がわかります。
是非お楽しみにしていてください。